ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > バリアフリーのまちづくり > 心のバリアフリーについて考えませんか
更新日:2025年9月18日
ここから本文です。
心のバリアフリーについて考えませんか
「バリアフリー」の「バリア」とは、英語で障壁(かべ)という意味です。バリアフリーとは、生活の中で不便を感じること、さまざまな活動をしようとするときに障壁になっているバリアをなくす(フリーにする)ことです。
施設のバリアフリー化に代表されるハードの整備が進んでも、高齢者や障がい者等に対して市民一人ひとりがやさしさや思いやりを持って接することができなければ、真の意味でのバリアフリーが実現することにはなりません。
高齢者や障がい者等の自立した日常生活や社会生活を確保することの重要性について関心を持ち、理解を深め、自然に支えあえるよう、「心のバリアフリー」について考えてみませんか。
心のバリアフリーとは
「心のバリアフリー」とは、さまざまな心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことです(「ユニバーサルデザイン2020行動計画(2017年2月ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定)」より)。
そのためには、一人一人が具体的な行動を起こし継続することが必要です。各人がこの「心のバリアフリー」を体現するためのポイントは、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」では、以下の3点とされています。
(1)障がいのある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障がいの社会モデル」を理解すること。
(2)障がいのある人(およびその家族)への差別(不当な差別的取扱いおよび合理的配慮の不提供)を行わないよう徹底すること。
(3)自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。
障がいのある人が社会で直面しているバリア
一般に「物理的なバリア」、「制度的なバリア」、「文化情報面のバリア」、「意識上のバリア」の4つのバリアがあるといわれています。
(1)物理的なバリア
公共交通機関、道路、建物などにおいて、利用者に移動面で困難をもたらす物理的なバリアのことを言います。
例:路上の放置自転車、狭い通路、急こう配の通路、ホームと電車の隙間や段差、建物までの段差、滑りやすい床など。
(2)制度的なバリア
社会のルール、制度によって、障がいのある人が能力以前の段階で機会の均等を奪われているバリアのことを言います。
例:学校の入試、就職や資格試験などで、障がいがあることを理由に受験や免許などの付与を制限するなど。
(3)文化情報面のバリア
情報の伝え方が不十分であるために、必要な情報が平等に得られないバリアのことを言います。
例:視覚に頼ったタッチパネル式のみの操作盤、音声のみによるアナウンス。点字・手話通訳のない講演会など。
(4)意識上のバリア
周囲からの心無い言葉、差別、無関心など、障がいのある人を受け入れないバリアのことを言います。障がいに対する誤った認識から生まれます。
例:精神障がいのある人は怖いといった偏見。障がいがある人に対する無理解、奇異な目で見たりかわいそうな存在だと決めつけたりすることなど。
心身機能の障がいについて
心身機能の障がいは、その種類、その程度によってさまざまなものがあります。同じ人でも周囲の環境や体調によって異なりますので、明確に分類することは困難です。主な心身機能の障がいを紹介します。
(1)視覚に障がいのある人
全く見えない(全盲)、光が感じられる(光覚)、メガネなどで矯正しても視力が弱い(弱視)、見える範囲が狭い(視野狭さく)、色の見え方が異なる(色覚異常)などさまざまです。
(2)聴覚に障がいのある人
全く聞こえない人(ろう者)、聞こえにくい人(難聴者)など、聞こえ方には個人差があり、外見からはわかりにくいです。声を出して話すことが難しい人もいます。
(3)肢体に障がいのある人
まひなどで、手や足など身体のどこかが動かない、あるいは動かしにくい状態にある人がいます。身体に力が入らなかったり、自分の意思とは関係なく動いてしまったりと、さまざまな状態があります。
(4)身体の内部に障がいのある人
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓や免疫機能など、身体の内部に障がいがあり、外見からはわかりにくいです。 一般的に疲れやすかったり、長時間立っていることが難しかったり、頻繁にトイレに行く必要がある人などがいます。
(5)知的障がいのある人
知的機能を中心とする精神の発達が幼少期から遅れていて、おおむね18歳までに障がいの判断を確定します。未経験なことが苦手だったり、複雑な事柄の理解や判断、社会生活の適応に困難さがあったりします。自分の考えや気持ちの表現(コミュニケーション)に困難さのある人もいるなど、大きな個人差があります。
(6)発達障がいのある人
生まれつき言語の発達の遅れや、不注意・多動性・衝動性、読み書きや計算が苦手、感覚が過敏であるなど、症状はさまざまです。社会生活や日常生活に支障が生じていることが多くあります。反対に優れた能力が発揮されている場合もあります。
(7)精神障がいのある人
ストレスなど生活環境の変化により発症するなど、誰もがなる可能性のある脳機能障がいです。薬や病気の影響で思考に時間がかかることがあります。生活環境の状況によって病状が変動しやすいため、周囲の人の理解やサポートが支えになります。
心のバリアフリーを理解し、行動しよう
一人ひとりが、「社会にあるバリアを理解したい」、「社会にあるバリアフリーの取り組みについて知りたい」などといった気持ちを持つことが、意識上のバリア解消の一歩となります。
(1)障がいの社会モデルの視点でバリアを理解しよう
人間関係を含めた社会との関係によってバリアが作られることを理解し、さまざまな人々がともに暮らしていることを意識することが必要です。
人々の意識や施設の不備など、社会や環境など、さまざまなことからバリアが作られていることを理解することで、そのバリアを除去するためにできることが見えてきます。
(2)コミュニケーションをとりましょう
バリアにより支障を受けている人に対して、どのような配慮が必要か、コミュニケーションをとり、意向を確認し、その人の意思を尊重することが大切です。「何かお手伝いできることはありますか」と話しかけたり、相手に応じてメモを見せたり、身振りを用いるなど、工夫してコミュニケーションをとりましょう。
(3)適切な配慮を行いましょう
バリアを解消して、本人が希望する活動を可能にすることであり、そのために適切な配慮を行うことが大切です。
本人が満足しているか、コミュニケーションを通じて確認しながら、行動することが重要です。
バリアフリーに関するサイン、シンボルマークを知ろう
バリアフリーに関するサイン、シンボルマークの一例を紹介します。
 障がい者のための国際シンボルマーク
障がい者のための国際シンボルマーク
障がいのある人が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
※このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障がいのある人を限定し、使用されるものではありません。
 盲人のための国際シンボルマーク
盲人のための国際シンボルマーク
世界盲人連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚に障がいのある人の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。
 身体障がい者標識(身体障がい者マーク)
身体障がい者標識(身体障がい者マーク)
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
 聴覚障がい者標識(聴覚障がい者マーク)
聴覚障がい者標識(聴覚障がい者マーク)
聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
 ほじょ犬マーク
ほじょ犬マーク
身体障がい者補助犬法の啓発のためのマークです。
身体障がい者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障がいのある人が身体障がい者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障がい者差別に当たります。
補助犬はペットではありません。社会のマナーもきちんと訓練されており、衛生面でもきちんと管理されています。
補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。
 耳マーク
耳マーク
聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークです。また、窓口等に掲示されている場合は、聴覚に障がいのある人へ配慮した対応ができることを表しています。
聴覚に障がいのある人は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。
このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法等への配慮(口元を見せゆっくり、はっきり話す・筆談で対応する・呼ぶときは傍へ来て合図する・手話や身振りで表すなど)について御協力をお願いします。
 ヒアリングループマーク
ヒアリングループマーク
「ヒアリングループマーク」は、補聴器や人工内耳に内蔵されているTコイルを使って利用できる施設・機器であることを表示するマークです。
このマークを施設・機器に掲示することにより、補聴器・人工内耳装用者に補聴援助システムがあることを知らしめ、利用を促すものです。
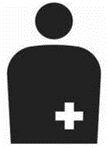 オストメイト用設備/オストメイト
オストメイト用設備/オストメイト
オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に障がいのある人のことをいいます。
このマーク(JIS Z8210)は、オストメイトの為の設備(オストメイト対応のトイレ)があることおよびオストメイトであることを表しています。
このマークを見かけた場合には、身体内部に障がいのある人であることおよびその配慮されたトイレであることを御理解の上、御協力をお願いします。
 ハートプラスマーク
ハートプラスマーク
「身体内部に障がいがある人」を表しています。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障がいがある方は外見からは分かりにくいため、さまざまな誤解を受けることがあります。
内部障がいの方の中には、電車などの優先席に座りたい、障がい者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障がいへの配慮について御理解、御協力をお願いします。
 「白杖 SOS シグナル」普及啓発シンボルマーク
「白杖 SOS シグナル」普及啓発シンボルマーク
白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障がいのある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。
白杖によるSOSのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをお願いします。
※駅のホームや路上などで視覚に障がいのある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSOSのシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをお願いします。
 ヘルプマーク
ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS規格)。
ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。
 手話マーク
手話マーク
聞こえない・聞こえにくい人が手話言語でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共および民間施設・交通機関の窓口、店舗など、手話言語による対応ができるところが提示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに提示することもできます。
きこえない・きこえにくい人等がこのマークを提示した場合は「手話言語で対応をお願いします」の意味、窓口等が提示している場合は「手話言語で対応します」等の意味になります。
 筆談マーク
筆談マーク
聞こえない・聞こえにくい人、音声言語に障がいのある人、知的機能に障がいのある人や外国人などが筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共および民間施設・交通機関の窓口、 店舗など、筆談による対応ができるところが提示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに提示することもできます。
きこえない・きこえにくい人等がこのマークを提示した場合は「筆談で対応をお願いします」の意味、窓口等が掲示している場合は「筆談で対応します」等の意味になります。
 ベビーカーマーク
ベビーカーマーク
ベビーカーを利用しやすい環境づくりに向けて作成されたマークです。公共交通機関や公共施設などのエレベーター、鉄道やバスの車両スペースなどに表示され、安全な使用方法を守った上でベビーカーを折りたたまずに利用できるなど、ベビーカーを安心して利用できる場所・設備をあらわしています。
 大分あったか・はーと駐車場
大分あったか・はーと駐車場
「あったか・はーと駐車場」を利用する方に利用証を交付する制度で、駐車場に設置するマークです。公共施設や店舗などの車いすマーク駐車場を適正にご利用いただくため、障がいのある方や、介護の必要な方、妊産婦の方など、車の乗降や歩行が困難な方に、県が共通の利用証を交付するものです。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
